ガロア理論の縁の下の力持ちと言っていいデデキントの補題を解説します。
ガロア理論は5次以上の方程式が解けるための必要十分条件を記述するために開発されました。
ガロアが理論を打ち立てた当初は難解すぎて理解されませんでしたが、デデキントが彼の理論を発掘して
初めて大学でガロア理論の講義をおこないました。
そんなデデキントの補題を今回は扱っていきます
デデキントの補題の主張
まずは主張の内容を確認しておきましょう。
以下です。
(デデキントの補題)
$K, L$を体とし、$K$から$L$への互いに異なる$n$個の準同型写像を
$\sigma_1, \sigma_2, \cdots, \sigma_n$とする。
このとき、任意の$x \in K$に対して、
$a_1\sigma_1(x)+a_2\sigma_2(x)+\cdots+a_n\sigma_n(x)=0$
($a_1, a_2, \cdots, a_n \in L$)
が成り立つのは
$a_1=a_2=\cdots =a_n=0$のときのみである。
「$K$から$L$への互いに異なる$n$個の準同型写像」
という文言がありますが、より正確には環準同型です。
難しく色々書いてあるように見えますが、
要するに
$\sigma_1(x), \sigma_2(x), \cdots, \sigma_n(x)$が
線形独立である、というのがメインの主張です。
最初は細かい所はこだわらずにざっくり雰囲気をつかんでいきましょう。
デデキントの補題は線形独立についての主張。
これで十分です。
線形独立という言葉に馴染みのない方はぜひ以下の記事をご覧ください

デデキントの補題はガロア理論においてかなり重要なもので、
これを土台として次々に定理たちが示されていきます。
ではなぜデデキントの補題はガロア理論でそれほどまでに重要なのでしょう?
鑑賞のポイントは、「体」と「並べ替え」です。
ガロア理論はそもそも方程式についての理論でした。
そして、方程式を解くということは係数の「体」の世界を解の世界まで広げることです。
その際に「対称式の基本定理」と「解と係数の関係」のコンボが便利でした。
対称性を数学的に記述するためには「並べ替え」に注目することが大切でした。
ゆえに「体」と「対称性」を結びつける道具が必要で、
それが自己同型写像でした。
さらに、自己同型写像は解の並べ替えを引き起こすことが分かっています。
詳細については以下の記事をご覧ください。
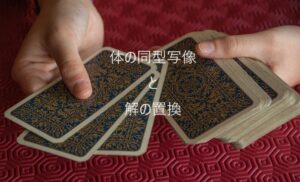
ここまでの流れを念頭においてデデキントの補題を見てみると、
まず線形独立が目につきます。
線形独立であるかどうかは、体の拡大次数を調べる際にとても重要な道具です。
ゆえに、線形独立は実質的に「体」の話につながっていく基礎的な内容と思ってください。
次に、準同型写像$\sigma$について。
$\sigma$は自己同型写像ではなくただの準同型写像なので、
若干一般的な話になってます。
準同型→同型→自己同型の順番で議論が深まっていき、
自己同型は並べ替えを引き起こします。
$\sigma$の部分は後に「並べ替え」についての話題につながっていく基礎的な内容と思ってください。
デデキントの補題は、「体」を分析するための基礎的な道具と
「並べ替え」を分析するための基礎的な道具の両方を含むような内容なので、
方程式についての理論であるガロア理論で重要な役割を演じるのです。
とは言ってみたものの。
いきなりこの主張を見てもちょっとよく意味がわからないと思うので、
具体例を見てみましょう。
デデキントの補題の具体例
デデキントの補題では、
2つの体$K, L$と$K$から$L$への準同型写像が登場します
(正確には環準同型ですがここではざっくりでOKです)
少々特殊な例ですが、
例えば、$K=\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, $L=\mathbb{Q}(\sqrt{2})$としてみましょう。
写像については、とりあえず$\mathbb{Q}(\sqrt{2})$から$\mathbb{Q}(\sqrt{2})$への自己同型写像を考えます。
これを$\sigma$と表すことにし、
$(\sqrt{2})^2-2=0$に着目すると、
$\sigma \lbrace (\sqrt{2})^2-2 \rbrace =\sigma(0)$
となります。
$\sigma$は四則演算を保存するので、
$\lbrace \sigma(\sqrt{2})\rbrace^2-2=0$
となり、
$\lbrace \sigma (\sqrt{2}) \rbrace^2=2$
から、
$\sigma(\sqrt{2})=\pm \sqrt{2}$
と分かります。
$\sigma_1(\sqrt{2})=\sqrt{2}$
と
$\sigma_2(\sqrt{2})=-\sqrt{2}$
としましょう。
いま、$x \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$を任意にとります。
また、$a_1, a_2 \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$を取ります。
このとき、
$a_1\sigma_1(x)+a_2\sigma_2(x)=0$
を考え、これがなりたつのが$a_1=a_2=0$のときのみであればよいです。
いま、$x \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$なので、
$x=\alpha+\beta\sqrt{2}$ ($\alpha, \beta \in \mathbb{Q}$)
と表されます。
これを
$a_1\sigma_1(x)+a_2\sigma_2(x)=0$
に代入します。
$a_1 \sigma_1(\alpha+\beta\sqrt{2})+a_2\sigma_2(\alpha+\beta\sqrt{2})=0$
$a_1(\alpha+\beta\sqrt{2})+a_2(\alpha-\beta\sqrt{2})=0$
$(a_1+a_2)\alpha+(a_1-a_2)\beta\sqrt{2}=0$
これでこのまま係数比較に持ち込んで、
$(a_1+a_2)\alpha=0$
$(a_1-a_2)\beta=0$
と立式したいところですが、今これを実行することはできません。
なぜか?
$(a_1+a_2)\alpha \in \mathbb{Q}$
かつ
$(a_1-a_2)\beta\in \mathbb{Q}$
であるならば係数比較ができます。
($\mathbb{Q}(\sqrt{2)$は$\mathbb{Q}$上の線形空間なので、
$1$と$\sqrt{2}$が線形独立であることが直ちに使えます)
でも今回は$a_1, a_2 \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$なのです。
ゆえに、
$(a_1+a_2)\alpha+(a_1-a_2)\beta\sqrt{2}=0$
↑この式の先に進むのに係数比較は使えません。
ではどうするか?
$\alpha, \beta $は$\mathbb{Q}$の任意の元です。
要するに、$\mathbb{Q}$のすべての元$\alpha, \beta$について
$(a_1+a_2)\alpha+(a_1-a_2)\beta\sqrt{2}=0$
は成り立たなければなりません。
なので例えば、
$\alpha=1, \beta=0$
のときも
$(a_1+a_2)\alpha+(a_1-a_2)\beta\sqrt{2}=0$
は成立していなければなりません。
すると、
$(a_1+a_2)×1+(a_1-a_2)×0×\sqrt{2}=0$
より
$a_1+a_2=0\cdots ①$
となります。
また、$\alpha=0, \beta=1$の時も
$(a_1+a_2)\alpha+(a_1-a_2)\beta\sqrt{2}=0$
は成り立たなければならないので、
$(a_1+a_2)×0+(a_1-a_2)×1×\sqrt{2}=0$
より
$a_1-a_2=0\cdots ②$
です。
まとめると、
$a_1+a_2=0\cdots ①$
$a_1-a_2=0\cdots ②$
となります。
連立方程式ですね。
$①+②$より、
$2a_1=0$で$a_1=0$です。
①に代入すると、直ちに$a_2=0$も分かります
よって今回の例ではデデキントの補題が正しいことが確認されました。
今回、最終的に連立方程式の形に持ち込んだ点を留意しておいてください。
定理の証明を行う際には、具体例の考え方を一般化する作戦が有効だからです。
デデキントの補題の証明
ではデデキントの補題の証明をしていきます。
今一度主張を確認しておきましょう。
(デデキントの補題)
$K, L$を体とし、$K$から$L$への互いに異なる$n$個の準同型写像を
$\sigma_1, \sigma2, \cdots, \sigma_n$とする。
このとき、任意の$x \in K$に対して、
$a_1\sigma_1(x)+a_2\sigma_2(x)+\cdots+a_n\sigma_n(x)=0$
($a_1, a_2, \cdots, a_n \in L$)
が成り立つのは
$a_1=a_2=\cdots =a_n=0$のときのみである。
さて、どうやって証明しましょうか?
まずは、主張の一番肝となる部分である、
「$a_1\sigma_1(x)+a_2\sigma_2(x)+\cdots+a_n\sigma_n(x)=0$
が成り立つのは$a_1=a_2=\cdots =a_n=0$のときのみである」
という部分に着目しましょう。
登場人物は、$a, x, \sigma, n$です。
青マーカー部分を、どの文字についての主張と考えるかが重要です。
デデキントの補題は、要するに線形独立について主張しています。
なんのために線形独立について議論したいのか?
それは、体の拡大次数の話につなげていきたいからです。
体の拡大次数はそのように定められていたか?
それは基底の数によって定まります。
$a, x, \sigma, n$で既定の本数に関わるのはどれか?
$n$です。
ゆえに、デデキントの補題は$n$についての内容であると捉えましょう。
$n$は自然数です。
自然数についての主張を証明する際に何を使ったでしょうか?
そう。
数学的帰納法です!!
ということは、$n=k$の仮定を使って$n=k+1$の場合を示すことになります。
どうするか?
今回のキーポイントは、
$a_1\sigma_1(x)+a_2\sigma_2(x)+\cdots+a_n\sigma_n(x)=0$
が足し算であるということ。
$k+1$個の足し算をなんとかして$k$個の足し算の話に落とし込むことができればOKです。
ではどうやって一つ項を消去するか?
加減法です!つまり、連立方程式で一文字消去したのと同じノリで、
引き算を用いて一つ項を消去します。
そのためには、$n=k$の場合の仮定に加え、
もう一つ式を立式しなければなりません。
そこで、$\sigma_i$ $(i=1, 2, \cdots, n)$は互いに異なるという条件を上手く使います。
ここまでの流れを踏まえたうえで証明へと進んでいきましょう!
(デデキントの補題の証明)
$a_1\sigma_1(x)+a_2\sigma_2(x)+\cdots+a_n\sigma_n(x)=0$
が成り立つのは
$a_1=a_2=\cdots =a_n=0$のときのみであることを、
$n$についての数学的帰納法で示す。
$n=1$のとき、
$a_1\sigma(x)=0$
となる。
ここで、$K$の乗法単位元を$1_K$とし、$L$の乗法単位元を$1_L$とする。
$x$は$K$の任意の元であるので、
$x=1_K$とすると、
体の間の準同型写像の性質から$\sigma(1_K)=1_L$である。
これを$a_1\sigma(x)=0$に代入すると、
$a_1\sigma(1_K)=0$
$a_1・1_L=0$
$a_1=0$
ゆえに、$n=1$ではデデキントの補題の主張は正しい。$\cdots ㋐$
$2≦k$となる自然数$k$を取り、$n=k$でデデキントの補題の主張が成り立つと仮定する。
このとき、$n=k+1$でもデデキントの補題が成立することを示す。
$a_1\sigma_1(x)+a_2\sigma_2(x)+\cdots+a_{k+1}\sigma_{k+1}(x)=0$
が成り立つのは$a_1=a_2=\cdots =a_{k+1}=0$のときのみであることを示せばよい。
いま、$x$は$K$の任意の元である。
各$\sigma_i$ $(i=1, 2, \cdots, k+1)$は互いに異なるので、
$\sigma_1(x) \neq \sigma_{k+1}(x)$となる
$x \in K$が存在する。
この$x$を$x=\alpha$と表すことにする。
$\alpha x \in K$である。
今、$a_1\sigma_1(x)+a_2\sigma_2(x)+\cdots+a_{k+1}\sigma_{k+1}(x)=0$
について、$x$を$\alpha x$に置き換えると、
$a_1\sigma_1(\alpha x)+a_2\sigma_2(\alpha x)+\cdots+a_{k+1}\sigma_{k+1}(\alpha x)=0$
となる。$\sigma_i$ $(i=1, 2, \cdots, k+1)$について、
$\sigma(\alpha x)=\sigma_i(\alpha)\sigma(x)$が成り立つので、
$a_1\sigma_1(\alpha)\sigma_1(x)+a_2\sigma_2(\alpha)\sigma_2(x)+\cdots +a_{k+1}\sigma_{k+1}(\alpha)\sigma_{k+1}(x)=0 \cdots ①$
となる。
また、
$a_1\sigma_1(x)+a_2\sigma_2(x)+\cdots+a_{k+1}\sigma_{k+1}(x)=0$
の両辺を$\sigma_1(\alpha)$倍すると、
$a_1\sigma_1(\alpha)\sigma_1(x)+a_2\sigma_1(\alpha)\sigma_2(x)+\cdots+a_{k+1}\sigma_1(\alpha)\sigma_{k+1}(x)=0 \cdots ②$
となる。
$①-②$をすると、$a_1\sigma_1(\alpha)\sigma_1(x)$の項は消去され、
$a_2\lbrace \sigma_2(\alpha)-\sigma_1(\alpha)\rbrace \sigma_2(x)+\cdots +a_{k+1}\lbrace \sigma_{k+1}(\alpha)-\sigma_1(\alpha)\rbrace \sigma_{k+1}(x)=0 \cdots ③$
となる。この左辺は$k$個の項の和である。
帰納法の仮定より、互いに異なる$k$個の写像についてはデデキントの補題が成立するので、
③が成立するのは
$a_i\lbrace \sigma_i(\alpha)-\sigma_1(\alpha) \rbrace =0$ $(i=2, 3, \cdots, k+1)$
のときのみである。
特に
$a_{k+1}\lbrace \sigma_{k+1}(\alpha)-\sigma_1(\alpha) \rbrace =0$
に着目すると、$\alpha$の定義より
$\sigma_{k+1}(\alpha) \neq \sigma_1(\alpha)$
であるので、
$\sigma_{k+1}(\alpha)-\sigma_1(\alpha) \neq 0$
となる。ゆえに
$a_{k+1}\lbrace \sigma_{k+1}(\alpha)-\sigma_1(\alpha) \rbrace =0$
から、$a_{k+1}=0$でなければならない。$\cdots ④$
ここで、
$a_1\sigma_1(x)+a_2\sigma_2(x)+\cdots+a_{k+1}\sigma_{k+1}(x)=0$
に$a_{k+1}=0$を代入すると、
$a_1\sigma_1(x)+a_2\sigma_2(x)+\cdots+a_{k}\sigma_{k}(x)=0$
となる。仮定より、互いに異なる$k$個の写像についてはデデキントの補題が成り立つので、
$a_1\sigma_1(x)+a_2\sigma_2(x)+\cdots+a_{k}\sigma_{k}(x)=0$
が成り立つのは$a_1=a_2=\cdots =a_k=0$
のときのみである。$\cdots ⑤$
④⑤より、
$a_1\sigma_1(x)+a_2\sigma_2(x)+\cdots+a_{k+1}\sigma_{k+1}(x)=0$
が成立するのは
$a_1=a_2=\cdots =a_{k+1}=0$
のときのみであることが分かり、
$n=k+1$でもデデキントの補題は正しいことが示された。$\cdots ㋑$
㋐㋑より、数学的帰納法から、全ての自然数$n$についてデデキントの補題が正しいことが示された。
(証明終了)
まとめ
いかがでしたか?
デデキントの補題はつかみどころのないものなので、いきなり見ても困惑すると思いますが、
具体例を見ると納得できます。
特に証明で数学的帰納法を使う点や、謎に引き算を使う点も、
具体例でデデキントの補題を確かめるときに連立方程式を使った点を考えると、
加減法の応用で文字消去のためにあのような変形をしていたと分かります。
次回はアルティン流ガロア理論の根幹を担う定理を、
デデキントの補題を用いて証明していきますので、ご期待ください。
また次回の記事でお会いしましょう!
参考
[1] エミール・アルティン, ガロア理論入門, 筑摩書房, 2010
[2] 中島匠一, 代数方程式とガロア理論, 共立出版, 2006
画像素材提供(アイキャッチ):https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dedekind.jpeg

コメント