円分多項式の既約性の証明、第2弾。
今回は、素数のべき乗次の円分多項式の既約性を示します。
その際にアイゼンシュタインの既約判定法を改造して使いますので、
注目です。
おさらい
まず、円分多項式とは何か?
(定義)
$\zeta_n=\cos \dfrac{2\pi}{n}+i\sin \dfrac{2\pi}{n}$とする。
このとき、
$\Pi_{GCD(n, k)=1, 1≦k≦n}(x-\zeta_n^k)$
を円分多項式といい、$\Phi_n(x)$で表す
このヤバい式で定義された$\Phi_n(x)$が円分多項式です。
定義だけ見るとヤバいですが、扱う式は案外シンプルな形をしています。
例えば、$n=4$を考えましょう。
$GCD(4, k)=1$となる$k$を探すところから開始です。
1,2,3,4のうち、4と互いに素なのは1,3ですので、
$\Phi_4(x)=(x-\zeta_4)(x-\zeta_4^3)=(x-i)(x+i)=x^2+1$
となります。
つまり
$\Phi_4(x)=x^2+1$
です。
円分多項式は、いくつか著しい性質が成り立ちます。
(円分多項式の性質①)
$x^n-1=\Pi_{d|n}\Phi_d(x)$
が成り立つ
これ結構すごいことを言っています。
例えば、$n=12$の場合を確認してみましょう
$x^{12}-1=(x-1)(x+1)(x^2+x+1)(x^2+1)(x^2-x+1)(x^4-x^2+1)$
と因数分解されるのですが、これを円分多項式の定義を使って書き換えると
$x^{12}-1=\Phi_1(x)\Phi_2(x)\Phi_3(x)\Phi_4(x)\Phi_6(x)\Phi_{12}(x)$
となります。
みごとに12の約数の円分多項式が並ぶのです!
ヤバいですよね!
また、この因数分解の式を使うと、
円分多項式が整数係数の多項式であることも証明できます
(円分多項式の性質②)
円分多項式$\Phi_n(x)$は整数係数多項式である
円分多項式の性質①と②の証明が気になる方は、ぜひこちらの記事をご覧ください。
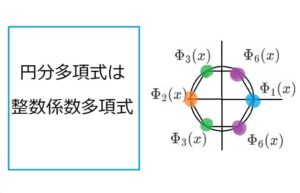
さて。
円分多項式は整数係数の多項式。
ここまでは比較的すぐ導くことができます。
前回は、素数次の円分多項式が整数係数の範囲で既約であることを示しました。
$\Phi_3(x)$とか、$\Phi_5(x)$とか、$\Phi_7(x)$とかです。
証明では、アイゼンシュタインの既約判定法が大活躍しました。
今回は
$\Phi_9(x)$とか$\Phi_{27}(x)$とか$\Phi_{25}(x)$とか、
素数のべき乗次の円分多項式が既約であることを示します。
今回もアイゼンシュタインの既約判定法に活躍してもらいたいのですが、
そのままではうまく使えないので、改造版を使います。
素数のべき乗次の円分多項式の既約性
まずはアイゼンシュタインの既約判定法をおさらいしましょう
(定理:アイゼンシュタインの既約判定法)
整数係数の多項式
$f(x)=a_nx^{n}+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots +a_1x+a_0$
に対して、以下の3つの条件を満たす素数$p$が存在するとき、
$f(x)$は有理数係数の範囲で既約な多項式となる。
① $a_n$は$p$で割り切れない
② $a_i$ $(i=0, 1, 2, \cdots, n-1)$ は$p$で割り切れる
③ $a_0$は$p$で割り切れるが、$p^2$では割り切れない
今回は素数のべき乗次の円分多項式を扱います。
その際に現れる多項式は
①の条件と②の条件は満たすのですが、③の条件を上手く満たさないんです。
そこで、アイゼンシュタインの既約判定法を改造します。
(定理:改造版アイゼンシュタインの定理)
整数係数の多項式
$f(x)=a_nx^{n}+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots +a_1x+a_0$
に対して、以下の3つの条件を満たす素数$p$と自然数$e$が存在するとき、
$f(x)$は有理数係数の範囲で可約かもしれないが、
多くとも$e$個の因数にしか分解できない。
① $a_n$は$p$で割り切れない
② $a_i$ $(i=0, 1, 2, \cdots, n-1)$ は$p$で割り切れる
③ $a_0$は$p$でちょうど$e$回割り切れる
青色マーカー部分がオリジナルと比べて改造した部分です。
証明はマジ長いので、後回しにするとして、
先に円分多項式の既約性を示そうと思います。
(素数のべき乗次の円分多項式の既約性)
$p$を素数とし、$e$を自然数とする。
このとき、円分多項式
$\Phi_{p^e}(x)$
は整数係数の範囲で既約となる
証明で押さえておきたいポイントは、二項定理を使うために$x$を$x+1$に置き換えるという点です。
これは素数次の円分多項式の既約性の証明と同じ流れではあるものの、やはり重要です。
(証明)
$\Phi_{p^e}(x)$について、円分多項式の性質②より、これは整数係数の多項式である。
また、$p^e$の正の約数は
$1, p, p^2, \cdots, p^e$
である。
したがって、円分多項式の性質①より、
$x^{p^e}-1=\Phi_1(x)\Phi_{p}(x) \Phi_{p^2}(x) \cdots \Phi_{p^e}(x)$
という因数分解ができる。
ここで、$\Phi_1(x)=x-1$であったので、
$\dfrac{x^{p^e}-1}{x-1}=\Phi_{p}(x) \Phi_{p^2}(x) \cdots \Phi_{p^e}(x)$
となる。
ここで、
$\dfrac{x^{p^e}-1}{x-1}=F_n(x)$とおくことにする。
$F_n(x)=\Phi_{p}(x) \Phi_{p^2}(x) \cdots \Phi_{p^e}(x)$
である。
これは$x$についての恒等式であるので、
$F_n(x)=\Phi_{p}(x) \Phi_{p^2}(x) \cdots \Phi_{p^e}(x)$
$⇔$
$F_n(x+1)=\Phi_{p}(x+1) \Phi_{p^2}(x+1) \cdots \Phi_{p^e}(x+1)\cdots ①$
である。
$F_(x+1)=\dfrac{(x+1)^{p^e}-1}{(x+1)-1}$
右辺に二項定理を適応した後、約分して整理すると、
$F_n(x+1)=x^{p^e-1}+{}_{p^e}\mathrm{C}_1x^{p^e-2}+{}_{p^e}\mathrm{C}_2x^{p^e-3}+\cdots +{}_{p^e}\mathrm{C}_{1}$となる。
(定数項のところは、${}_n\mathrm{C}_r={}_n\mathrm{C}_{n-r}$を使っています)
${}_{p^e}\mathrm{C}_i$ $(1≦i<p^e)$
が$p$の倍数であることと、${}_{p^e}\mathrm{C}_1=p^e$
であることを踏まえると、
$F_n(x+1)$は改造版アイゼンシュタインの定理の条件①②③を満たすので、
どんなに多くとも$e$個の因数しかもたない。
①の式より、すでに$f_n(x+1)$は$e$個の因数に分解されている。
ゆえに、これより多くの因数を持ちえない。
したがって、
$\Phi_p(x+1), \Phi_{p^2}(x+1), \cdots, \Phi_{p^e}(x+1)$
は整数係数の範囲で既約でなければならない。
したがって、
$\Phi_p(x), \Phi_{p^2}(x), \cdots, \Phi_{p^e}(x)$
も既約である。
(証明終了)
お疲れさまでした!
ここまでお読みいただきありがとうございます。
本日の記事のメイン内容は以上です!
ここからは軽く補足を。
二項定理で出現した二項係数
${}_{p^e}\mathrm{C}_k$ $(1≦k<p^e)$
が$p$の倍数になるという部分を説明します。
$p^e$じゃなくて$p$のときは大学入試でもたまに使いますね。
あれとほぼ同様の議論なのですが、微妙にちょっとだけ応用です。
${}_{p^e}\mathrm{C}_k=\dfrac{p^e!}{k!(p^e-1)!}=\dfrac{p^e×(p^e-1)!}{k×(k-1)!(p^e-1)!}$
$=\dfrac{p^e}{k}×\dfrac{(p^e-1)!}{(k-1)!(p^e-1)!}=\dfrac{p^e}{k}{}_{(p^e-1)}\mathrm{C}_{(k-1)}$
となり、
${}_{p^e}\mathrm{C}_k=\dfrac{p^e}{k}×{}_{(p^e-1)}\mathrm{C}_{(k-1)}$
となります。
よって
$k×{}_{p^e}\mathrm{C}_k=p^e×{}_{(p^e-1)}\mathrm{C}_{(k-1)}$
となります。
$k$が$p^e$と互いに素な場合は、右辺が$p^e$の倍数であることから必然的に
${}_{p^e}\mathrm{C}_k$は$p^e$の倍数となります。
$k$が$p^e$と互いに素でない場合は、$k=p^h$となり、$h<e$なので、
両辺を$p^h$で割ると、
${}_{p^e}\mathrm{C}_k=p^{e-h}{}_{(p^e-1)}\mathrm{C}_{(k-1)}$
となり、$p^{e-h}$の倍数です。
いずれにしても、$p$の倍数であることは確実です。
改造版アイゼンシュタインの既約判定法の証明
ここからの内容は本当におまけです
(定理:改造版アイゼンシュタインの定理)
整数係数の多項式
$f(x)=a_nx^{n}+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots +a_1x+a_0$
に対して、以下の3つの条件を満たす素数$p$が存在するとき、
$f(x)$は有理数係数の範囲で可約かもしれないが、
多くとも$e$個の因数にしか分解できない。
① $a_n$は$p$で割り切れない
② $a_i$ $(i=0, 1, 2, \cdots, n-1)$ は$p$で割り切れる
③ $a_0$は$p$でちょうど$e$回割り切れる
これを証明します。
この証明は、ただ面倒なだけなので、
興味のある方以外は読み飛ばして次の見出しに進んでください
もうほんと、この証明は飛ばしても全く無問題です。
マジめっちゃ長いですよ?
いいですね?
マジで長いので、一応区切りのところでマーカーをつけておきました。
では、証明していきましょう!
(証明)
整数係数の多項式
$f(x)=a_nx^{n}+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots +a_1x+a_0$
に対して、以下の3つの条件を満たす素数$p$と自然数$e$が存在するとする。
① $a_n$は$p$で割り切れない
② $a_i$ $(i=0, 1, 2, \cdots, n-1)$ は$p$で割り切れる
③ $a_0$は$p$でちょうど$e$回割り切れる
条件③より、$a_0$は$p^e$の倍数なので、$p$と互いに素な自然数$k$を用いて
$a_0=kp^e$
とする。
いま、$f(x)$が既約な場合は、因数は1つとみなせるので、
$1<e$より、改造版アイゼンシュタインの定理は真である。
ここで、$f(x)$が整数係数の範囲で可約であるとする。
すると、整数係数の多項式
$g(x)=b_sx^s+b_{s-1}x^{s-1}+\cdots +b_1x+b_0$
$h(x)=c_tx^t+c_{t-1}x^{t-1}+\cdots +c_1x+c_0$
によって、
$f(x)=g(x)h(x) \cdots ㋐$
と因数分解できる。
㋐において、両辺の次数は等しいので、
$n=s+t$
である。
ここで、㋐の最高次の係数を比較すると、
$a_n=b_sc_t$
となる。
条件①より、$a_n$は$p$で割り切れないので、
$b_s, c_t$のいずれも$p$で割り切れない。
(ここからほぼアイゼンシュタインの既約判定法の記事と同じ内容が続きますが、少々お付き合いください)
いま、㋐より、$f(x)$は整数係数の多項式$g(x)$と$h(x)$によって因数分解されている。
ここで、「$g(x)$の最高次の係数以外のある係数が$p$の倍数にならないか、
または$h(x)$の最高次以外の係数のある係数が$p$の倍数にならない」と仮定する。
$g(x)$の最高次の係数以外のある係数のうち、$p$の倍数とならない最小のものが$j$次の係数$b_j$ $(0≦j<s)$だったとする。
㋐について、$j+t$次の係数を比較する。
$a_{j+t}=b_{j+t}c_0+\cdots b_{j+1}c_{t-1} +b_jc_t \cdots ㋑$
(計算してみると分かりますが、添え字の和が$j+t$になるやつらを足すことになります)
㋑の左辺について、
$b_j$の定義より、$b_{j+1}, b_{j+2}, \cdots, b_{j+t}$
は全て$p$の倍数でなければならない。
したがって、左辺の
$b_{j+t}c_0+\cdots b_{j+1}c_{t-1} $
は$p$の倍数である。
簡略のため、これを$pM$とおく $(Mは整数)$
すると、㋑の式は
$a_{j+t}=pM+b_jc_t\cdots ㋒$
となる。
条件②より、$a_{j+t}$は$p$の倍数である。
㋒について、$a_{j+t}$が$p$の倍数で、$pM$も$p$の倍数であるので、
$b_{j}c_t$も$p$の倍数でなければならない。
ここで、$b_j$の定義より、これは$p$の倍数ではない。
また、$c_t$は$h(x)$の最高次の係数のため、これも$p$の倍数ではない。
ゆえに、$b_jc_t$は$p$の倍数になりえないが、これは矛盾。
よって、
「$g(x)$の最高次の係数以外のある係数が$p$の倍数にならないか、
または$h(x)$の最高次以外の係数のある係数が$p$の倍数にならない」という仮定が間違っていた
ということになり、背理法より、
「$g(x)$の最高次の係数以外の任意の係数が全て$p$の倍数で、
かつ$h(x)$の最高次以外の係数以外の任意の係数も全て$p$の倍数である」
ということになる。
ここで、㋐の式について定数項に着目すると、
$a_0=b_0c_0$
である。$a_0=kp^e$で、かつ$b_0$も$c_0$も$p$の倍数であるので、
$b_0=k_1p^{e_1}, c_0=k_2p^{e_2}\cdots ㋓$
($k_1, k_2, e_1, e_2$は自然数)
となる。
$g(x)$と$h(x)$がともに既約な場合は、
$f(x)$は2つの因数に分解されることになる
$2<e$よりこの場合も改造版アイゼンシュタインの定理は真である。
$g(x)$または$h(x)$が可約な場合は、
ここまでの議論の$f(x)$を$g(x), h(x)$にすり替えることにより、
$g(x)=g_1(x)g_2(x)$
$h(x)=h_1(x)h_2(x)$
のように因数分解でき、
$g_1(x), g_2(x), h_1(x), h_2(x)$はそれぞれ最高次以外の係数が全て$p$の倍数です。
特に、定数項は$p$のべき乗の倍数になっており、$p$で$e_k$回だけ割り切れる。
$(1≦e^k<e)$
$g_1(x), g_2(x), h_1(x), h_2(x)$も可約で次々に整数係数の多項式に分解されたとすると、
最終的に定数項が$p$で1回だけ割り切れる多項式までは同じ議論が適応できる。
このような多項式を$p_i(x)$ $i=1, 2, \cdots, e$とすると、
$f(x)=p_1(x)×p_2(x)×\cdots ×p_e(x)$
となる。
$p_i(x)$ $(i=1, 2, \cdots, e)$
は、最高次以外の係数が$p$の倍数で、定数項は$p$で1回だけ割り切ることができ、$p^2$では割り切れない。
したがって、(オリジナルの)アイゼンシュタインの既約判定法より、
$p_i(x)$ $(i=1, 2, \cdots, e)$
は整数係数の範囲で既約である。
よって、$f(x)$は可約であったとしても$e$個までしか因数をもたない。
以上のことから、改造版アイゼンシュタインの定理が示された
(証明終了)
まとめ
いかがでしたか?
・素数のべき乗次の円分多項式は既約
・素数次の場合の方法をうまく使いまわして、二項定理に持ち込む
・アイゼンシュタインの既約判定法は、そのままは使えないが、改造すると使える
以上を押さえていただければと思います。
ではまた次回の記事でお会いしましょう!
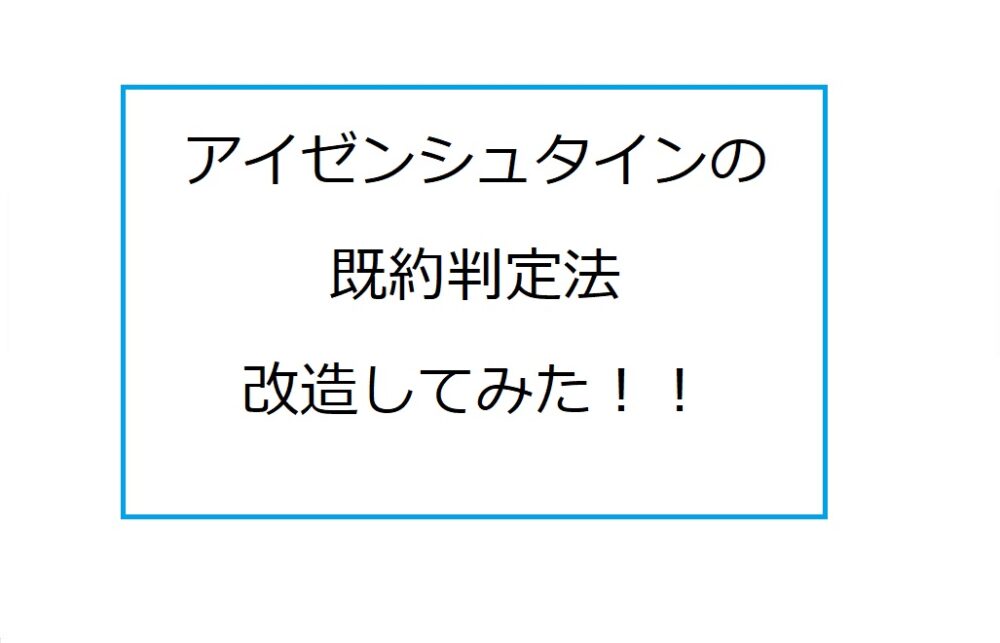
コメント